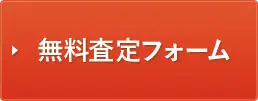グレーズ技法とは、透明もしくは半透明の絵の具を薄く塗り重ねる絵画技法のことです。「グラッシ」や「ウェット・オン・ドライ」と呼ばれることもあります。「釉薬」という意味を持つ英語「Glaze(グレーズ)」が由来で、焼き物に薄く釉薬を乗せるのに似ていることからグレーズ技法という名称が付きました。
グレーズ技法には長い歴史があり、中世には水彩画やテンペラ画に用いられていました。15世紀になると、油絵でも使われるようになります。近年はグレーズ技法で使える透明な絵の具が販売されていますが、昔は油をたくさん使ったり絵の具を大幅に薄めたりして塗り重ねていました。絵の具を乗せ、乾いたら二層目の着色を行い、何度も透明な絵の具を重ねていくのが基本の制作手順です。
色を何度も塗り重ねるため、複雑な彩色や深みのある色の表現ができるのが、グレーズ技法の特徴です。また下に塗った色を透かせるので、微妙な陰影や凹凸を表現しやすいのも特色として挙げられます。下から透ける色をもとにさらに精密に書き込むことも容易になるため、グレーズ技法は絵画制作において欠かせない技術と言えるでしょう。
グレーズ技法を用いた作品としては、現在のベルギーで生まれたヤン・ファン・エイクの『ファン・デル・パーレの聖母子』が挙げられます。中央にいる人物が身につけている赤い服にはグレーズ技法が用いられており、単色で塗りつぶすよりも深みがあり、リアルな立体感や質感が表現されています。