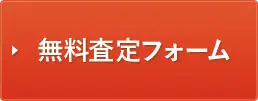静物画とは、花、野菜、果物、楽器、本といった動かないものを描いた絵画作品のことです。西洋画のジャンルのひとつで、古代ローマ帝国の時代から制作されていたと考えられています。古代ローマ帝国崩壊後は作例があまり見られなくなりましたが、15世紀ごろから宗教画や豪華本の挿絵などで取り入れられるようになりました。
静物画が西洋画のジャンルとして確立したのは、17世紀以降のことです。特にオランダはプロテスタントを信仰していたこともあり、宗教画の需要が少なかったため、静物画が絵画の主流ジャンルのひとつでした。
当時はヨーロッパ全体では人物画や宗教画が主流だったため、静物画はあまり評価されていませんでしたが、19世紀になると注目を集めるようになります。セザンヌやゴッホをはじめとした印象派の画家が静物画を制作し、後世のフォービズムやキュビズムにも影響を与えたと考えられています。
一方東洋では静物画はあまり発達せず、動かないものだけをテーマにした作品はほとんど制作されませんでした。日本では、幕末以降に静物画が描かれるようになったとされています。
静物画を細分化すると、花束、朝食画・晩餐画、コレクション画などに分類されます。朝食画・晩餐画では、人物が描かれず、豪華なテーブルの様子だけを表現するのが特徴です。
代表的な作品としては、15世紀のフランドル地方の画家ハンス・メムリンクが描いた『花瓶の花』、朝の食卓の風景を描いた『蟹のある朝食』、セザンヌの『リンゴの籠のある静物』、ゴッホの『ひまわり』などが挙げられます。