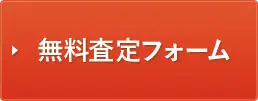壺屋焼(つぼややき)とは、沖縄県那覇市壺屋を中心に生産されている陶器のことです。地元では「焼物(やむちん)」とも呼ばれており、沖縄を代表する陶器として知られています。14~16世紀の琉球王国は東アジア諸国との貿易を盛んに行っており、同時期に大陸から伝わった高麗瓦が由来とされています。
17世紀になると琉球王国は薩摩藩の支配下に置かれ、外国との貿易もあまり行われなくなりました。このことを危惧した琉球王国の尚貞王は、薩摩藩から朝鮮人の陶工を招き、産業振興の一環として製陶技術の習得に注力します。1682年になると王府内にあった窯を現在の壺屋に統合し、現在の壺屋焼が完成しました。
明治時代になると安価な焼物の大量生産による影響で下火になりますが、大正時代には民芸運動が高まり、壺屋焼も注目されるようになります。1985年には陶芸家の金城次郎が沖縄初の人間国宝に指定され、壺屋焼の存在も広く知られるようになりました。
壺屋焼の特徴は、沖縄ならではの色鮮やかな絵付けが施されることです。庶民が使う器もカラフルに彩られ、特に泡盛を注ぐための酒器が盛んに生産されています。
荒焼(あらやち)と上焼(じょうやち)の2種類に分類されるのも、壺屋焼の特徴として挙げられます。荒焼は釉薬をかけずに1120度くらいで焼き上げる焼物で、水甕や酒甕といった大型の焼き物が作られます。上焼はさまざまな種類の釉薬で絵付けを施して1200度の高温で焼き上げたもので、茶碗・皿・カラカラなどの日用品が多く作られています。