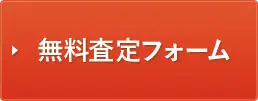花押とは、自身の署名の代わりに用いられる記号や符号のことです。起源は草書体とされており、草書体で書かれた自署の形や筆順が通常の文字とは異なり、特殊な形状になったものが花押と呼ばれています。元々は文書に記載する自署として使われており、次第に図案化・文様化が進み、多用な形状の花押が生まれました。
花押は東アジアの広い範囲で使われており、日本では古いものだと平安時代に書かれたものがあります。11世紀になると、実名に使われている2文字を組み合わせた形の花押が登場しました。当初は貴族社会のみで使われていましたが、11世紀後期には庶民の文書でも花押が用いられるようになります。戦国時代になると花押の様式が多様化し、漢字を裏返したり倒したりして書いたものや、実名以外の文字をもとに作られるようにもなりました。
江戸時代になると花押はさらに広まり、印章と同様の使われ方がされていました。しかし江戸中期には花押を使用する人が減り、代わりに印鑑が用いられるようになります。1873年には実印のない証書は証拠にならないという法律ができ、花押はほとんど使われなくなりました。
花押は日本以外でも使われており、中国では南北朝時代にまで遡るという説もあります。朝鮮半島では宋の影響を受けて花押が用いられるようになり、「着署」「草押」とも呼ばれていたようです。中国は現存する古文書が少なく、花押の実態は不明な点が多いのですが、朝鮮半島では公文書だけでなく民間の私文書でも、自署を表現するために使われていました。