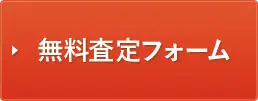上野焼(あがのやき)とは、現在の福岡県田川郡香春町、福智町、大任町で生産されている陶器のことです。豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に、加藤清正が連れ帰った朝鮮の陶工、金尊楷が窯を作ったのが始まりとされています。当時小倉藩を治めていた細川家の統治下で成長し、歴代藩主の御用達にもなりました。
江戸時代中期になると、徳川家で茶道を教えていた小堀遠州という人物によって「遠州七窯」のひとつに数えられ、茶人からも好まれるようになります。しかし明治時代には廃藩置県の影響で、上野焼は衰退します。その後明治35年になると田川郡の補助によって再興され、昭和58年に国の伝統的工芸品に指定されました。
上野焼の特徴は、他の陶器よりも薄手で軽量であることです。ろくろで成形した粘土を乾燥させるときは、屋内で2~3週間かけてじっくりと乾かします。また、使用する釉薬の種類がとても豊富なのも上野焼の特色のひとつです。青緑釉、白褐釉、黄褐釉など、さまざまな釉薬を用います。窯の中で釉薬が変化する風合いを楽しむため、絵付けをほどんど施さないのも上野焼ならではの特徴です。
なかでも代表的な釉薬は、酸化銅を使用した緑青釉です。焼き上がると鮮やかな青色に発色します。焼き上がった陶器の手触りもさまざまで、柚子の皮のような感触の「柚肌」、虫食いのような粒が洗われる「虫喰釉」、2つの土を使って木目の文様を表現する「木目」などがあります。素材本来の特性を活かし、自然な変化や風合いを楽しめるのが上野焼の魅力です。