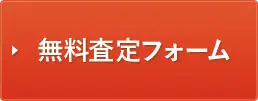出石焼(いずしやき)とは、兵庫県豊岡市出石町で生産されている磁器のことです。1764年に、伊豆屋弥左衛門という人物が土焼窯を作ったことが、出石焼の始まりと考えられています。その後、二八屋珍左衛門という人物が出石藩からの援助を受け、有田(現在の佐賀県西部)で陶器の作り方を教わりました。
有田で陶器の作り方を学んだ後、二八屋珍左衛門は一度出石町に戻ってきましたが、資金難に陥り、丹波に移り住むことになります。出石町に残された職人は二八屋珍左衛門の意思を受け継ぎ、土焼き職人になったことで出石焼が伝承されました。江戸後期になると出石焼の生産が盛んに行われるようになり、「盈進社(えんしんしゃ)」という組織も作られました。
出石焼の特徴は、国内産の磁器としては珍しく白磁が作られているところです。白磁の原料が大量に見つかり、「柿谷陶石」という純白の原料を使用しているため、類を見ないほどの白さを誇ります。絹のような美しい白さは海外でも評価され、1904年にアメリカで開催されたセントルイス万国博覧会では金賞を受賞しました。
作品の表面に浮き彫りや透かし彫りといった装飾を施しているのも、出石焼の特徴のひとつです。ほかにも、模様を描いた素材を磁器に貼り付ける「貼花」という技法も用いられており、清廉かつ華やかな印象を与える作品がたくさん生産されています。茶器や食器だけでなく、現在は箸置きや風鈴なども作られており、お土産としても人気がある磁器です。