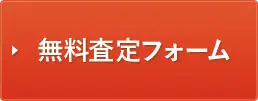唐三彩とは、中国で唐の時代に生産された陶器のことです。3種類の色が使われているものが多いことから、「唐三彩」と呼ばれています。色を表現する際は、主に鉛・銅・鉄などの釉薬を使用します。よく見られる色の組み合わせは、土の色(白)・緑・黄(茶)や、クリーム色・藍・紫です。
唐三彩の形は、人・動物・器の3種類に大別できます。盛んに生産されていたのは唐の時代ですが、唐三彩が発見されたのは1900年代に入ってからです。鉄道工事をしている時に出土したとされています。その後各地で発掘調査を行った結果、かつて都が置かれていた長安や洛陽を中心に、中国全土で見つかりました。
唐三彩は、中国国内では王侯貴族の墓に埋葬するために作られていたと考えられています。ほかにもシルクロードの交易を通じ、シリア・キプロス・イタリアなどにも伝わっています。日本では奈良時代に遣唐使が唐三彩の情報を持ち帰ることで、伝来したようです。唐三彩を参考に、奈良三彩が作られました。一時期は世界中で流通した唐三彩ですが、時代の流れとともに生産されなくなりました。
唐三彩は粘土を成形した後、2回焼成するのが基本的な作り方です。1回目は粘土の形を整えた状態で、1,000~1,100度の窯で素焼きにします。冷却した後、素焼きしたものに釉薬をかけ、再度850~950度で焼成します。完成した唐三彩は時間が経過するごとに釉薬の色が浸透するため、色合いが少しずつ変化していくのが特徴。釉薬には気泡が少なく、表面にはツヤがあるのも特色です。