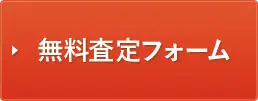四日市萬古焼(よっかいちばんこやき)とは、三重県四日市市で生産されている陶磁器のことです。江戸時代の元文年間(1736~1740)に、商人で茶が趣味であった沼波弄山という人物が、現在の三重郡朝日町小向に窯を築き、自分で茶器を焼いたのが始まりとされています。
自身の作品が永遠に残るよう願いを込めて「萬古」や「萬古不易」という印を押したことがきっかけで、「萬古焼」という名称が付いたと考えられています。沼波弄山の死後約30年間は四日市萬古焼の生産が中断しましたが、江戸後期になると、古物商の森有節・千秋兄弟によって再興されました。現在は100社以上の窯元があり、土鍋や皿などの日用品が盛んに生産されています。
四日市萬古焼の特徴は、耐熱性の高さです。とくに土鍋に使う陶器には、葉長石という熱に強い鉱石を粘土に40%ほど混ぜており、直火や空焚きにも対応できる耐熱性を備えています。粘土に葉長石を混ぜる技法は四日市萬古焼が特許を取得しており、他の産地では見ることができない方法です。国内で生産されている約80%の土鍋は、四日市萬古焼で生産されています。
土鍋のほかにも、急須には「紫泥」という鉄分を豊富に含む土を使用しており、使えば使うほど光沢が増していくのが魅力です。紫泥急須は、1979年に経済産業大臣指定の伝統的工芸品になりました。現在は毎年5月中旬に地元の窯元が作った作品を販売する「萬古まつり」を開催しており、生産開始から約300年経った今も人気を集めています。