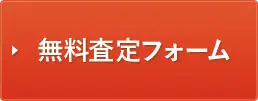土佐派とは、日本画の流派のことです。南北朝時代の藤原行光を祖としており、古くから続く大和絵の技法を継承しています。室町時代になると、その後約200年にわたって朝廷の絵所を世襲しており、宮廷文化の中で育まれた流派と言えます。とくに土佐光信の時代には宮廷や将軍家と深い関係を持ち、最盛期を迎えました。
室町時代末期になると、土佐光信の直系の孫である光元が但馬攻めで戦死し、朝廷の絵所を管理する職務を失ってしまいます。織田・豊臣の時代になると狩野派が躍進したことで、土佐派は大きく衰退。桃山時代には堺に拠点を移し、一次は狩野派の下請け業者のような立場になっていたようです。
しかし江戸時代には再び拠点を京都に戻し、1654年には土佐派の土佐光起が宮廷の絵所の職に復帰。土佐派は再興され、幕末まで地位を維持し続けました。土佐派の絵師が制作した作品には、土佐光信の『石山寺縁起絵巻』や『伝足利義政像』、土佐光起の『北野天神縁起絵巻』などが挙げられます。重要文化財に指定されている作品も多数あり、土佐派は日本の美術史を形作る重要な存在と言えるでしょう。
土佐派は昔ながらの大和絵の技法を受け継いでおり、繊細で装飾性の高い画風が特徴です。土佐光起の時代には、狩野派の力強い画風を取り入れた作品も制作されました。土佐光起や、土佐派から派生した住吉派の2代目住吉具慶の時代には新しい表現を用いていましたが、それ以降は新しいテーマや表現に挑戦することはあまりなく、伝統的な手法を受け継いでいきました。