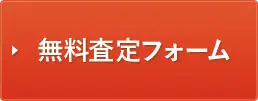大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)とは、福島県浪江町の大堀地区で生産されている陶器のことです。江戸時代中期の元禄3年(1690年)に開窯し、当時この地を治めていた相馬中村藩の保護・育成を受けながら成長しました。農家の副業としても普及し、相馬中村藩は大堀相馬焼を藩の特産物にしようとしました。
相馬中村藩は元禄10年(1697年)に大堀相馬焼の技術者等は藩の外に出ないよう布令を出して、技術流出を防ぎます。享保18年(1733年)には、瀬戸物は地元産のものを主に使用するよう布令して、大堀相馬焼の需要を確保しました。江戸時代末期には窯元が100戸を超えて、東北有数の陶器の産地にまで成長しました。
しかし明治時代になると、廃藩置県の影響で相馬中村藩からの援助が途絶え、大堀相馬焼の窯元は次々と閉窯することになります。その後は戦争による影響も受け、大きな打撃を受けましたが、終戦後は復活し、昭和53年(1978年)には国の伝統的工芸品に指令されます。
平成23年(2011年)3月の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、大堀相馬焼の産地は帰還困難区域に指定されました。震災前は20戸以上あった窯元のうち、現在は約半数が福島県内で生産を再開しています。
大堀相馬焼の特徴は、「青ひび」という青磁釉のひび割れが器全体に広がっているところです。不規則なひび割れが、柄模様のように見えます。実用性にも優れており、厚みがあって壊れにくいのも魅力。「二重焼」という独自の構造で、お湯が冷めにくく、熱い飲み物を入れても器を持ちやすいのも特長です。