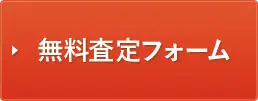大谷焼(おおたにやき)とは、徳島県鳴門市大麻町で生産されている陶器のことです。江戸時代後期の1780年に、豊後国(現在の大分県)から焼き物細工職人の文右衛門が大谷村を訪れ、赤土で陶器を作ったのが始まりとされています。1781年には11代藩主の蜂須賀治昭によって藩営の窯が作られ、盛んに生産されるようになりました。
しかし3年後には原材料費がかさんだため、藩営の窯は一度閉鎖されます。代わりに藍商人の賀屋文五郎が中心となり、日用品として使う陶器を焼く「連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま)」が作られました。連房式登窯では滋賀県で作られる信楽焼の職人を雇い、地元の人は技術を習得。その後、納田平次平衛が中心となって生産が再開され、現在の大谷焼に繋がっているとされています。
大谷焼の特徴は、鉄分を豊富に含んでいることです。手触りはザラザラとしており、表面には金属のような鈍い光沢があります。生産されている器は、茶碗や湯呑といった生活用品と、装飾品が中心です。主にこげ茶色の陶器が作られるほか、ときには鈍い銀色や灰色のものも生産されます。2003年に、国の伝統的工芸品に指定されました。
作り方の特徴としては、「寝ろくろ」という技法が用いることが挙げられます。寝ろくろとは、1人が横に寝転んで足でろくろを回し、もう1人が成形する方法です。大人の身長ほどある巨大な甕のような大きなものを作るときに用いる方法で、藍染め用の藍液を入れるための甕の需要があったため発展したと考えられています。