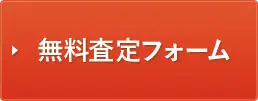小石原焼(こいしわらやき)とは、福岡県朝倉郡で生産されている陶器のことです。1682年に黒田藩3代目藩主の黒田光之が、伊万里焼の職人を招いて焼物を作ったのが起源とされています。主に酒壺・花器・茶器などの生活用品を生産していたようです。当初は当時の地名にちなみ、小石原焼は「中野焼」と呼ばれていました。
一時的に小石原焼は途絶えましたが、1927年に再興され、1958年にはベルギーの首都ブリュッセルで開催された万国博覧会でグランプリを受賞する等、大きく成長していきます。「用の美」というキャッチフレーズとともに注目を集め、1965年頃には受注生産から見込み生産へと生産体制が切り替わり、日本各地に出荷されるようになりました。1975年に国の伝統的工芸品にも指定され、現在では日本を代表する焼き物のひとつになっています。
小石原焼の特徴は、器をろくろで回しながら模様を付けることです。刃物を使って土を削ったり、刷毛・櫛・指などを粘土に当てたりして、規則的な模様を付けます。釉薬の付け方の種類も豊富で、等間隔に釉薬を付ける「流し掛け」、釉薬を容器から少しずつかける「ぽん描き」などの技術が用いられています。焼き上がった小石原焼は素朴で上品な風合いがあり、実用性と美しさを兼ね備えているのが魅力です。
小石原焼の生産は現在も続いており、茶碗・豆皿・箸置きといった日本の昔ながらの食器のほか、マグカップやカップ&ソーサーのような西洋風のものも登場しています。洗練された意匠と彩色が魅力で、今も多くの人からの注目を集めている陶器です。