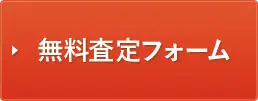斉白石(せいはくせき)とは、清末から中華人民共和国の画家のことです。書家や篆刻家としても活動し、現代中国画の巨匠として知られています。1864年に、当時の湖南省長沙府湘潭県の、貧しい農家の家に生まれました。7歳になると数カ月間初等教育を受けましたが、家計が困窮したため、独学で絵を勉強することになります。
13歳で家具職人になり、10余年間は木工を生業にしながら生活していました。27歳になってようやく本格手な絵の勉強を始め、文人画家の胡自倬のもとで花鳥画や鳥獣画を学びます。40歳以後7年間は中国全土を巡って芸術的な視野を広げ、その後はじっくりと作品の制作に取り組みます。55歳になると、北京に住居を移し、絵や印を売りながら生計を立てました。
当時の北京は保守的な風潮が強く、農家出身だった斉白石は冷遇されていました。しかし、日本への留学経験があった陳師曽が斉白石を支援し、1922年に東京で開催された日中共同絵画展をきっかけに、国際的な評価が高まりました。晩年は明の八大山人や石濤の影響を受けながら独自の画風を生み出し、1957年に亡くなりました。
斉白石の画風の特徴は、鮮やかな彩色と力強い墨を対比させたり、風景や花を大胆でデフォルメ化したりすることです。生物や草花をモチーフにした作品が多く残っています。伝統的な中国芸術を基礎としつつ、木工をはじめとした民間芸術を取り入れた独自の画風は「紅花墨葉(こうかぼくよう)」と呼ばれています。代表的な作品は、『蝉』や『墨蝦図』です。