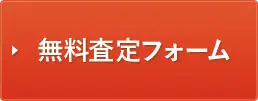横山大観とは、日本の画家のことです。1868年に、常陸国水戸(現在の茨城県水戸市)で生まれました。学生時代から絵画に興味を持っており、1889年に東京美術学校の1期生として入学。卒業後は京都に移って仏画の研究を行い、同時期から「大観」という雅号を使うようになりました。
西洋絵画の画法を取り入れた新しい画風の研究も行っていましたが、当時の画壇から強烈な批判を浴び、日本国内での活動が行き詰まり始めたため、海外に渡ります。インド、アメリカ、ヨーロッパなどを渡り歩き、欧米での評価が高まったことを受け1907年に帰国。以降は文部省美術展覧会の審査員への就任、日本美術院の再興などを経て画家としての地位を確立しました。
横山大観の画風の特徴は、「朦朧体」という画法を用いていることです。輪郭線を描かず、色の濃淡や形だけで空間を表現します。富士山や桜といった、日本ならではの自然をテーマにしているのも特色です。特に富士山は生涯にわたってテーマとし続け、「富士の画家」と呼ばれることがあります。横山大観は第二次世界大戦後も作品の制作を続け、1951年に文化功労者になります。1958年に、東京都台東区の自宅で永眠しました。
横山大観の代表的な作品としては、中国の春秋戦国時代の詩人である屈原をテーマにした『屈原』、小さな子どもが立ち尽くしている様子を描いた『無我』などが挙げられます。東京国立博物館所蔵の『瀟湘八景』や東京国立近代美術館所蔵の『生々流転』など、重要文化財に登録されている作品もあります。