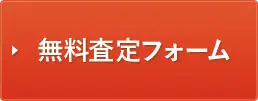津軽焼(つがるやき)とは、青森県弘前市で生産されている陶器のことです。津軽藩四代藩主の津軽信政が、津軽藩で陶磁器を自給自足することを目的に、陶工を集めて窯を作らせたのが始まりです。窯があった地名ごとに大沢焼・平清水焼・下川原焼・悪土焼と呼ばれ、その総称として「津軽焼」という呼び名が使われています。
津軽藩が治めていた時代は、日用品や調度品などさまざまな製品が造られていました。しかし明治時代になると、鉄道が開通したことで他県の焼き物が津軽にもたくさん入るようになります。津軽焼は他県の焼き物の勢いに押され、大正時代には一時断絶しました。現在生産されている津軽焼は、昭和時代になってから再興されたものです。
津軽焼の特徴は、釉薬の原料に青森の名産品であるりんごを使用しているところです。りんごの木灰を原料にした釉薬は「りんご釉」と呼ばれており、素朴な色合いの陶器が作られています。ほかにも、鉄分を豊富に含む「黒天目釉」という黒色の釉薬を使用することがあります。職人が1つ1つ手作りしており、作品ごとに異なる風合いを楽しめるのが魅力です。
津軽焼とよく似た名前の焼き物に、「津軽金山焼」というものがあります。津軽金山焼は、1985年に五所川原市の金山地区で生産が始まった、新しい焼き物です。釉薬を使わず1300度の高温でゆっくり焼き上げる製法を用いており、素材の質感を活かした独特の質感が特徴です。燃料である松の灰や火加減によってさまざまな模様ができ、津軽焼とはまた異なる魅力を感じられます。