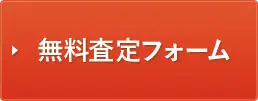笠間焼(かさまやき)とは、茨城県笠間市周辺で生産されている陶磁器のことです。江戸時代の箱田村(現在の笠間市)の有力者であった久野半右衛門道延が、信楽焼の陶工から焼き物づくりの指導を受けて始まったとされています。その後笠間藩の御用達の窯元として保護され、甕や食器などの日用品を生産するようになりました。
江戸に近いことから、幕末から明治にかけては大量生産を行うようになり、従事者も大きく増加。明治時代になると、厨房用の陶器の生産地として知られるようになりました。しかし終戦後は、生活様式の変化やプラスチックの普及などを受け、笠間焼は衰退します。厨房用の陶器生産から工芸陶器の生産に切り替え、1992年には国の伝統的工芸品に指定されました。
笠間焼の特徴は、耐久性の高さです。笠間焼には粒が細かくて粘りがある「蛙目粘土(がいろめねんど)」が使われており、衝撃や汚れに強い特性があります。毎日使っても傷みにくいことから、古くから厨房用の陶器として好まれていました。蛙目粘土には鉄分が豊富に含まれており、焼き上がると褐色に変化するのが特徴。絵付けを施すよりも、釉薬を掛けることでツヤを出した、素朴な作風も魅力のひとつです。
現在の笠間焼は厨房用の陶器だけでなく、花器・インテリア用品・芸術作品なども作られています。伝統工芸品のイノベーションの成功例としても知られており、競争力の強化や、生産額・観光客の増加によって地域経済に貢献したことなどが評価されています。時代の変化に柔軟に対応し、地域に根差しながら伝統を守り続けているのが笠間焼の魅力です。