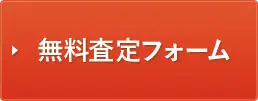長谷川派とは、桃山時代から江戸時代初期にかけて活動した日本画の画派のことです。1539年に現在の石川県七尾市で生まれた、長谷川等伯を祖としています。20代の頃から日蓮宗に関する仏画や肖像画を描いており、1571年に上洛してからは狩野派をはじめとした諸流派、牧谿や雪舟の水墨画などを幅広く学びました。
千利休や豊臣秀吉からも高く評価され、長谷川等伯は当時の画壇の頂点にあった狩野派を脅かす存在になります。そんな長谷川等伯には久蔵、宗宅、左近、宗也の4人の子がおり、全員が長谷川派の絵師として活動しました。とくに久蔵は等伯を超える存在とも言われていましたが、26の若さで亡くなり、宗宅が家督を継ぎます。
宗宅が亡くなった後は左近が後を継ぎ、等伯の画風を受け継ぎつつ俵屋宗達のような装飾性のある作品も残しました。宗也は、等伯の子ども4人のなかで最も系統が長く続きました。等伯の子ども以外にも弟子がいましたが、等伯の死後に優れた画家が出なかったためか、長谷川派は静かに表舞台から姿を消しました。長谷川派が制作した作品には、国宝や重要文化財に指定されているものが多くあり、短い活動期間で日本の美術史に大きな影響を与えたことが伺えます。
長谷川派の作品の特徴は、宋から清の画題・技法を用いる「漢画」の要素を多く取り入れているところです。とくに等伯は、中国の宋・元の画題や技法を用いた水墨画も多く残しました。長谷川派を代表する作品としては、等伯が制作した『松林図屏風』『松に秋草図』、宗宅の『秋草図屏風』などが挙げられます。