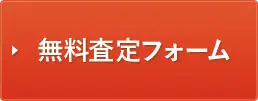青磁とは、青色や緑色の発色する釉薬を使用して作られた陶磁器のことです。主に日本や中国などで生産されています。紀元前14世紀ごろの中国で生産が始まったとされており、当時は植物の灰を使った釉薬で焼成していたため、草色だったと考えられています。青い青磁が作られ始めたのは、1~3世紀ごろです。
日本に青磁が伝来したのは平安時代ごろで、当初は貴族の間で重宝されました。現在の愛知県名古屋市の東部から豊田市の間にあった、猿投窯(さなげよう)という窯で生産が始まったと考えられています。鎌倉時代から安土桃山時代にかけて茶の湯が流行するのに合わせ、茶道具としても好まれました。江戸時代には独自に発展した青磁が登場し、鍋島焼や三田焼などが生産されるようになります。
青磁の特徴は、不規則に入っている貫入(かんにゅう)です。貫入とは、青磁に入っているヒビの模様のこと。焼き上がった陶磁器の温度が下がるとき、素地と釉薬の収縮具合に差があることで、釉薬にヒビが入る場合があります。貫入には色が付くこともあり、陶磁器を構成する要素のひとつとして鑑賞する際は注目されています。
よく知られている青磁の種類は、浙江省の龍泉窯で作られた「砧青磁(きぬたせいじ)」、深い緑色の光沢がある釉薬をたっぷりかけた「天龍寺青磁(てんりゅうじせいじ)」、明の中期から後期にかけて制作された「七官青磁(しちかんせいじ)」などです。青磁茶碗の『馬蝗絆』や花瓶の『青磁下蕪花生』は、日本で国宝に指定されています。